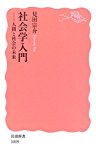自分が社会学系の本を好きになったきっかけは、ある本です。大学へ入学したての頃、社会学部の方に薦めてもらった見田宗介先生の『社会学入門』という新書です。その中で紹介されていたある俳句が目に留まりました。
手向くるや むしりたがりし 赤い花
まず、この句を読んでどのように思えたか。
...
...口ぽかーん
だったのを覚えてます。
もともと少年ジャンプしか読んでこなかったので仕方ないです。
ところで、この句、どんな意味が込められてると思いますか?
手向(たむ)くるとは、有難いものに手を向ける=供える。
あとの部分は、むしりたがった赤い花、
を意味するそうです。これだけ聞いてもパッとしません。
この句は、小林一茶が、可愛がっていた幼子が亡くなったときに詠まれた俳句なのだそうです。
さらにあるエピソードがこの本の中で紹介されます。
民俗学者レヴィ=ストロースが著書『野生の思考』を執筆しているときのことです。
アメリカの原住民は、自分たちと白人の違いについて、現代人の着目する違いよりも先に「白人は平気で花を折るが自分たちは花を折らない」ということを挙げた、とのことです。
これは比較社会学の核心に触れる問題なのだそうですが、それはそうと見田先生は、その句の読まれた江戸時代にも花が咲き乱れていた、と補足します。
そして、それは畏(おそ)れと感動に満ちたものの一つだった、なので、幼い子でも花をむしることは止められていた。だから、この句は
「あんなにむしりたがっていた赤い花だよ」
と一茶がその子に手渡すように詠んだ句だ、と紹介されて、改めてその句を読んでみると
...
たむくるや むしりたがりし 赤い花
...
素晴らしい句だ..
と思わされたんで、不思議です。ところで、今では意味を知ったので、面白いと思わされますが、それまで写真ばかり撮っていた自分には新鮮でした。フレームの中に、良い感じで活字が混ざってきた感じがしました。