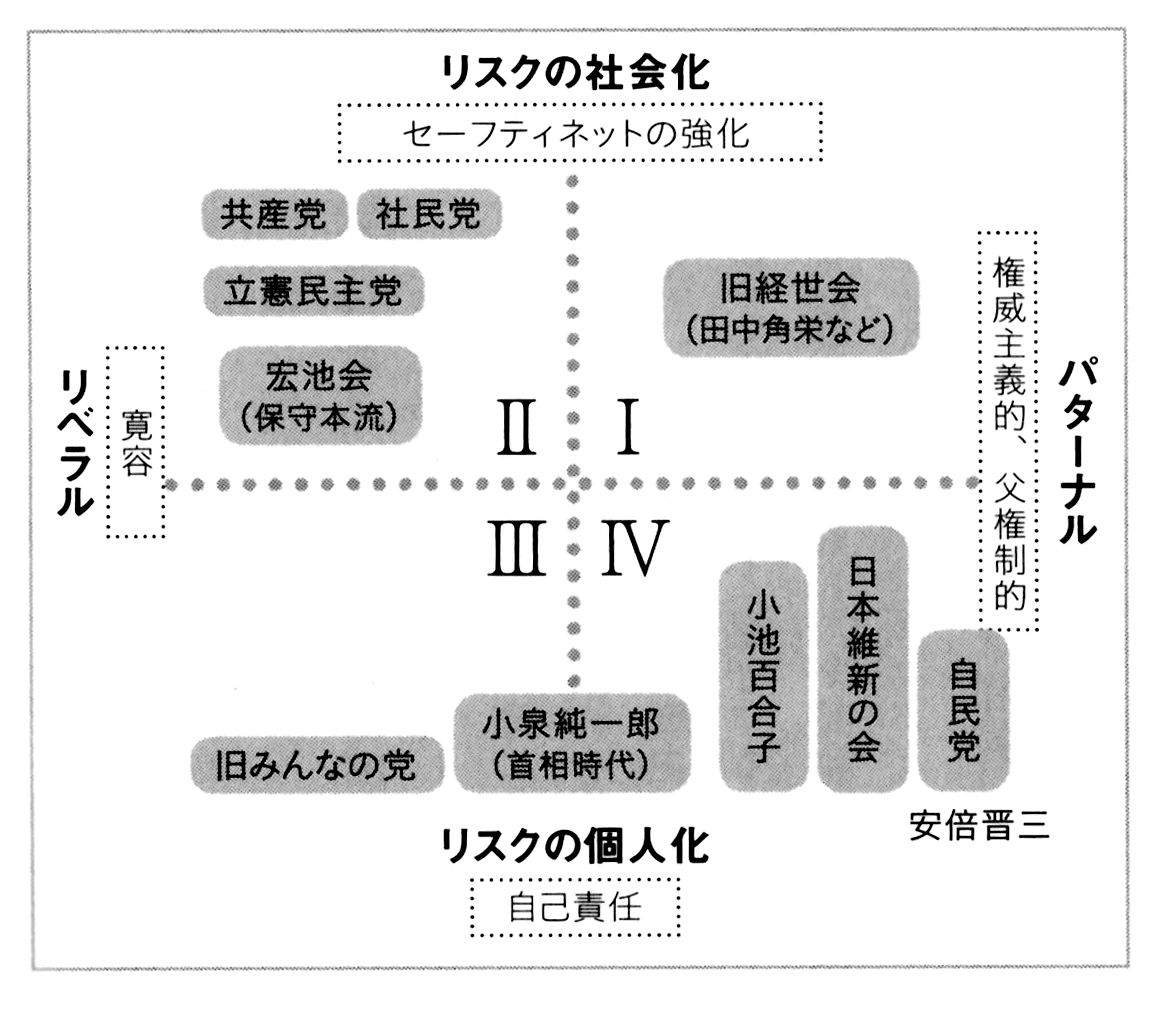第33回MK学習会 1月26日
参加者4名

『明暗』(夏目漱石 1987 改版 新潮文庫)を取り上げました。
夏目漱石の遺作です。
この作品は、複数の出版社から発刊されており、4社の文庫版を用意することができました。学習会のために購入した新潮社版を含め、他の3社の『明暗』を集めていただいたパートナーにも感謝です。おかげでそれぞれ異なる解説に触れることができました。
ところで、新潮社の改訂版は、令和4年、47刷です。解説の執筆は柄谷行人さんでした。他社と比べると、もっとも多く増刷されたのがこちらの新潮社の版で、上記の相関図の頁数もこの版を用いました。
残りの三社の版について言えば、岩波文庫の改訂版が、2010年、26刷で、解説は大江健三郎さん。
角川文庫、集英社のものが、どちらも初版で、それぞれの解説は、山城むつみさん、佐古純一郎さんでした。
____
『明暗』の登場人物はほとんど誰一人、素直ではないようです。腹のうちを見せず、意地とプライドをひた隠す登場人物を中心に、親族内での葛藤が綴られます。妻・延子は、何一つ不足のない夫(津田)を持った妻として、表面的には取り繕います。実際には、お延は津田に満足してはいなかった、と語られます。
手をかえ品をかえ、登場人物は、そのまた別の登場人物に干渉します。吉川夫人は、のらりくらりと立ち振る舞う津田自身に、根本治療が必要であることを示唆します。それも、まさに余計なお世話と思われるような方法で、です。様々な歪みが随所に生じており、友人の小林の卑屈は、夫婦のそれぞれに露呈されます。
「親切なのかい、義務なのかい」と、妹・秀子に津田が問う場面がありますが、どの場面を切り取っても、エゴイスティックな断片が現れます。
漱石は、それでいて、登場人物の誰に対しても市民としての立場や、社会的な責任を担わせません。難しい哲学を語ることもありません。随所にさりげなく散りばめられた諧謔は、緊迫した文章の隙間から輝きを放つようで、漱石の筆力の高さに恐れ入りました。
しかし作品の真意は何だったのでしょう。ふと別の見え方が立ち上がりました。前回、取り上げた『文学とは何か』(加藤周一)で、個人主義やロマン主義の文学が普遍的な文学の要素になり得る、と語られたことを思い出します。一人の田舎娘を通して、孤独と平等の上に築かれる社会全体を語ることができると、ジャン=ジャック・ルソーの『告白』を評して語るほどでした。その加藤氏の賛ずる『明暗』は、どのように読まれたのか、思いが広がりました。
漱石の『明暗』は一種の家庭小説であり、その家庭的紛争は明らかに日本の社会の特殊性を反映していますが、『明暗』の場合には、そのような歴史的社会的条件の特殊性が小説家の捉えた現実ではなく、人間性に普遍的な愛や憎悪やその他諸々の情念こそ小説の中の真に現実的なものだと思います。
….その本質においては歴史的社会的条件を超えるという事実を暗示している。それは、すべての人間精神がその深いところでは一致するからに違いありません。p137『文学とは何か』加藤周一
加藤氏の言わんとするところは、『明暗』では、「すべての人間精神が深いところで一致する」、というものでした。歴史的社会的条件を超える、とも語られます。条件とは、とりもなおさず、家制度や権利問題など歴史に付随する市民の社会的諸条件だろうと思います。それを超えることを、漱石は暗示している、とまで記述されます。一方、ルソーの作品では個人主義の原理に着目されます。
ルソオ以前には、ありふれた田舎女の心の中に、人間に関する一切があると考えるものはなかった...。しかるに、ルソオは、自己の内心に一切があると考えた…p152
ありふれた人間の内心の告白に、文学的価値を認めるということは、人間をその本性・自然において、平等なものとして認めるということです。P155『同書』加藤周一
再び、メタ視点から『明暗』を振り返ります。
『明暗』では、誰の未来も、社会も、目的も、描かれません、それは先ほど書いたことに重なりますが、登場人物は、ただ、そうせざるを得ないそれぞれの事情を持っており、そうしなければ他にやりようがなかった、仕方がなかった。という差し迫る状況に置かれ、次々と詮索と駆け引きに耽ります。
作品中では、自らの世間体によって窮迫する人物や、自らの傲慢さに疲弊する人物が涙を流します。
漱石は、小林という卑屈な男を二度にわたって泣かせます。
はたから見れば過干渉にも見える人間関係の中で、もし、人が、泣くべくして泣くとしたら、読む人によっては、やりようのなさに鬱屈とするかもしれませんが、反対に、どうしても生きようとする人間の純粋さを、発見するかもしれません。
言葉巧みに人をやり込めたはずの人間が、気がついたら自分を苦しめ、生理的な衝動となって、感涙とともに自ずと本人に本音を白状させる。そのような警報機のような意識の流れが、漱石の描きたかったことならば、少なくともそこにある人間の衝突は、対等なものとして描かれたように思えます。差し迫った局面に直面させる切実さが、空間的な障害や人間関係の馴れ合いを乗り超えて、主張しあえる距離に本人を誘い出すように。
すると、過干渉に見えた対立は、実は人間の平等の裏返しなのかもしれません。ルソーの個人主義と平等が手の届きそうなところに見えてきます。
加藤氏の読み方は、そのような視点を想起させます。
一人、のらりくらり、回避を続けた津田が、決着の一歩を踏み出した時(温泉地にたどり着いた時)、ほどなくして、漱石の筆は絶たれます。その時、漱石のロマン主義が、特別な切実さを帯びたのかもしれません。
漱石がどこまで意図したのかは、わかりません...。仮に、加藤氏の視点から、この『明暗』の主人公が誰か?と問えば、おそらく登場人物の誰であるとか、人間の「エゴイズム」そのものである。といった回答ではもの足りない(と思います)。
それはむしろ、あらゆる社会制度や人権や倫理的インフラの根源にある人間の温かさや人間味である。だけでなく、もしかすると、そのさらに下に流れる特別な生理学的な情の原理を、主人公とした。とまで言わなくてはならない(と思います)。人間精神の深いところでの一致を、加藤氏は『明暗』に読み取るからです。
身勝手かもしれませんが、そのような印象が、『明暗』の感想となりました。夏目さんが聞いたら笑うかもしれませんが...
____
解説に関しては、柄谷さん、山城さん、佐古さん、どれも良かったのですが、特に大江健三郎氏の語る内容に目に止まるものがあり、抜粋して終わりたいと思います。
今回は、学習会は新年会と題して簡単な食事会に行きましたが、貴重な時間をありがとうございました。今回の著作も、個人的には好みのタイプだったようです。
次回も楽しみです。
…明暗に先立つ、漱石のいくつかの講演は、近代化日本の行く末を思いつつ、たとえエゴイズムとならざるをえぬにしても、自立した原理を持って自分を生かしてゆく必要を語るものだった。この小説に書かれた親戚を含む社会関係の中で、どのように自立して生きてゆくか?愛を擁立するか?困難だが必要なその実現のために、お延は戦うことを決意した人間である。
しかし自分が、「私」を確立することは、同じく「私」を確立している他人を認めることでなければならない。このようにして多様な「私」が自己を確立して生きる、その総体を認めよう。その総体を司るもの、つまり「天」の意思は、人間の狭いこの規模のプラス、マイナス、善悪を超えた原理かもしれないが、致し方はない。それが「則天去私」ということではないであろうか?
...彼が到達した「則天去私」という最終の思想は、決して楽観的なものではなかったにしても、根底に積極的な意思を潜めていたはずだと思うのである。p607